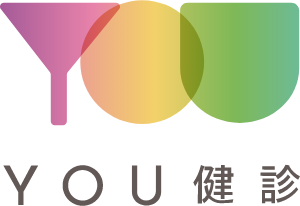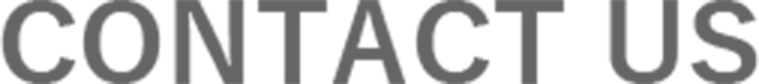株式会社資生堂
ピープル&カルチャー本部
ウェルネスサポートグループ
Interview
企業理念として、「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD」。美の力でよりよい世界を作ること、を掲げている資生堂。
社員の8割が女性という中で考える女性特有の健康課題についての想いをお聞きしました。
まずは、株式会社資生堂様の事業内容と理念を教えてください。

資生堂の事業内容は、スキンケア、メイクアップ、フレグランスなどの化粧品を中心とした製品の製造と販売をメインとしています。始まりは1872年。日本初の民間洋風調剤薬局として、東京銀座で創業し、現在では約120の国と地域で事業を展開しています。私たちの企業理念、使命としては、「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」。です。 私たちは、美には人の心を豊かにし、生きる喜びやしあわせをもたらす力があると信じています。 資生堂は創業以来、人のしあわせを願い、美の可能性を広げ、新たな価値の発見と創造を行ってきました。これまでもこれからも、美しく健やかな社会と地球が持続していくことに貢献します。
貴社では女性の方が多く在籍されているかと思いますが、女性の方の健康促進に向けた会社としての支援を具体的にお聞かせください。
弊社の社員は8割が女性で、店頭のスタッフはほぼ女性です。 2020年に社内で女性の健康プロジェクトがスタートし、2023年から本腰を入れ、3か年計画を立てました。2023年はまず更年期、2024年に月経・PMS、妊娠、不妊、プレコンセプションケア、2025年は適正体重、貧血、骨粗鬆症と、1年ごとに内容を変え、取り組みを行っています。 これに基づき、社員のヘルスリテラシーの向上と、働きやすい職場環境の形成を目的に社内イベントを開催するなど、Eラーニング、相談窓口の積極的周知等を行ってまいりました。社員に、正しい知識を提供し、自分自身で考える機会を創出することと、正しい情報を自分で選択し、自律的に健康行動につなげることを目指し、プロジェクトの施策を展開をしております。私たちは、この活動に「わたしらしく、エイジング」とネーミングをつけ、自分らしく、健やかに美しく年を重ねるすべての人を応援したいという想いをこめて、活動をしております。
2024年度の取り組みについて
2024年度の取り組みをご紹介すると、月経・PMS、妊娠、不妊、プレコンセプションケアにフォーカスしてまずは社内の実態調査から始めました。 その結果に基づき、イベントを開催したのですが、このイベントには社員のみではなく、同じ悩みを持ち奮闘している同業他社の産業保健に関わる方もご招待し、実施いたしました。 イベントにはトップマネジメントを初めとした役員や、産業医、保健師、現場の管理職が登壇しました。 男性役員も登壇してもらい、マネージメントという立場から考える、女性の身体のケアについてや、オープンに話し合える風土醸成のために必要なことについて、ご自身の経験を踏まえた、あたたかく、力強いメッセージを社員へ届けました。 こういった男性役員の参加が、社内全体で女性の健康に対する理解を深めて、より包括的なサポート体制を築くための一歩になったのでは、と考えています。 限られた人員と予算の中で、且つ隅々まで行き渡るような施策がないか、というのは日々プロジェクトメンバーで検討をしております。
年度によって、フォーカスするテーマを変えていますが、そのテーマはどのように決めていますか?

2020年にプロジェクト自体がスタートしましたが、それまでも単発的にセミナーなどは実施していました。 ただ、どうしても打ち上げ花火的に終わってしまうということがあり、そうならないよう、健診の結果や、社員構成、平均年齢を鑑みてインパクトの大きい所からアプローチをしていくことを考え、2023年は更年期の世代にフォーカスして取り組みを始めました。 3か年計画を立てる時に、まずは更年期だが、その次は若年層に向けた月経、PMSも大事だと思っていましたし、不妊、プレコンセプションケアもフォーカスしたいと思っていました。 その後は全社的に見るとメタボ、肥満は取り扱いやすかったのですが、女性が多く、特に若い女性の痩せも課題と感じていたので、適正体重や、そこから繋がる貧血、骨粗鬆症が重要なポイントと感じました。 アンケートで実態を調査し、その中から社員のニーズを把握し、こちらがやりたいことではなく、社員の課題や問題点にフォーカスし、アプローチすることが重要と考えています。
女性の方の健康促進に向けた施策や取り組みについて、どのように導入を決めていますか?

基本的にはプロジェクトメンバーで施策を検討し、マネージャーへ相談。その後部長クラスに提案し、最終確認を取りながら施策を進めています。 社員の健康を守るための大切な取り組みであると理解いただいており、部長以上も巻き込みながら活動をしています。
上記のような取り組みを導入されて、実際に社員様から反応はありましたか?
イベントを実施した際に、事後アンケートをとっており、どの取り組みも9割を超える理解度や、満足度となっています。 特に更年期、月経痛、PMSのイベントでは、トップマネジメントの体験談を話してもらうようなトークセッションを実施したのですが、その後のアンケートで、女性の社員から「トップマネジメントが自分事で考えてくれているのがよく分かった」「環境を整えてる大切さについて考えてくれているのがすごく嬉しかった」「社内の女性に勇気を与えてくれた」というような、ポジティブな反応をもらいました。 ネガティブな反応はほとんどないですが、イベント自体に男性社員ももっと参加してほしい、という意見をもらうことはあります。 性別問わず、どの世代でも女性特有の健康について理解を深め、一緒に支えあっていくことができるように、もう少し関心を持ってもらうような仕掛けづくりができるよう日々検討をしております。
イベントにはどのくらいの人数の方が参加されるのでしょうか?

イベントはオンライン含め、100~120人が参加しています。 イベント報告を後日イントラ配信していますが、延べ480名くらいの社員が視聴しています。 ただ、時間をつくることが難しいなどの理由から、参加やイントラ配信を確認することが難しい社員もいます。 特に店頭で働く社員は、応対に集中しているため、情報を得るのが難しくなっております。 もちろん、掲示板や社内の情報サイトはありますが、それを店頭でゆっくり見る時間がないので、どういう風に伝えていくことができるのかは検討し、施策に反映させたいと思っています。
女性特有の症状や疾患についての施策を会社に導入する際の障壁や課題があれば教えてください。
現状、そこまで大きな障壁や課題があるとは感じていません。 社員の8割が女性で、女性の管理職も多いという状況もありますが、出産・育児を終えて戻ってくる文化も根付いているので、チームが円滑に機能できるようサポートを厚くする必要はあると考えています。 また、弊社の医療職の声が社員に正しく伝わっていて、女性vs男性という構図にはなっていないと思っています。 女性には女性特有の身体の機能があり、ホルモンのバランスもあって、コントロールできないものなので、自分たちが正しい知識を持ち、予防、相談などで自分たちを活用してください、と何度も医療職が社員に伝えています。 男性にも、医療職が自分たちの言葉で、正しい知識を持って提案するので、なるほど、となって受け入れてくれています。 ただ、男性社員からも「男性の健康はケアしないのか?」という声もあがることはあります。 そのため、更年期のテーマの時は、男性更年期の話も含めてセミナーを実施したり、男性に登壇してもらうこともありました。 なるべく、女性だけの問題ではないですよ、と伝えるようにはしています。 「生物学的な性」や、「女性特有の健康」など、分かりやすく医療職が言葉を選ぶことにより、男性にも伝わりやすいものになっていると感じます。
女性特有の症状に対する施策等を実施するにおいて、男性社員からの理解を得られているような印象を受けますが、実際はいかがでしょうか。
月経のセミナーにも男性役員2名に登壇してもらいましたが、月経についての知識基盤がとてもあり、セミナーでも詳しく話せるんです。 なぜか聞いたところ、過去に社内で生理用品の担当をしていたことがあった役員でした。ビジネスに繋がっていたから、月経についての知識もついており、なじみがあったのでは、と思っています。 構造的に、女性のメンバーの事情を理解しておかないと、チームも仕事も成り立たないという状況はあると思います。 そのため、男性の管理職は、どういう風なコミュニケーションをとるか、どこまで言っていいのかなど、自分でも勉強されていると思います。
月経のセミナーで、役員に向けられた質問
先ほど申しあげた月経のセミナーでは、登壇した役員に質問が上がりました。 社員からは、「女性の部下とどういう風にコミュニケーションをとっていますか?」や、管理職からは、「どういう風に具合の悪い女性に接すればいいか分からない」、というご意見でした。 役員からの回答は、具合が悪い時だけに声をかけるのではなく、普段から挨拶できる、ちょっとした会話を交わせる関係性になっておくのが大前提、ということでした。 その中の延長として、「最近元気ないけどどうしたの?」という会話から始まるのでは、とのことでした。 それが性別問わずすべての答えな気がしました。 また、役員からのお願いとしては、「私たちはエスパーではないから、言ってもらわないと分からない。なので、言ってほしい。相談してほしい。今自分がつらいんだ、と声に出していいんだよ。」と伝えていたのがとても腹落ちしました。 上司部下、双方の歩み寄りが必要だと感じた瞬間でした。
様々な取り組みをされている資生堂様ですが、女性の健康経営についての想いや、課題感などがございましたら教えてください。

私たちの企業使命は、「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD(美の力でよりよい世界を)」です。 これを実現するためには、まずは資生堂で働く全社員が、自分たち自身が健康で豊かで幸せな生活を送ること、そして健やかな美を体現するということが重要であると考えております。 資生堂の社員の8割が女性のため、その女性たちが、健康で生き生きと働き続けられる環境を整えていくことが、企業理念の実現にも繋がると思います。 女性特有の健康課題に対する取り組みは、女性だけではなく男性も含めて、社員1人1人が自分事として捉えること、また、それらをオープンに語り合う、相談できる風土を築くことから始められればと思っています。 これにより、年齢や性別を問わず、すべての社員が健康に関する意識を高め、ともに支えあう文化を育んでいくことができるのでは、と思っております。
HUGYOUプロジェクトにご賛同いただいたお気持ち、想いをぜひお聞かせください。

社内でアンケートをとった際に、資生堂の社員は我慢をして働き続けている人が多い印象を受けました。 HUGYOUプロジェクトの話を伺ったときに、「働き続けたい女性に対して寄り添いたい」という想いだったので、その想いに共感し、賛同を決めました。 資生堂独自の施策を社内で展開しておりますが、賛同企業の皆様のお取組みや、ファムメディコが持っている知見を共有していただければ嬉しいなと思っております。 このプロジェクトを通して、資生堂の社員が、健康になっていくのはもちろん、それだけではなく全ての働く女性が生き生きと働けるということが今後目指していくべき所ではないか、と思っております。