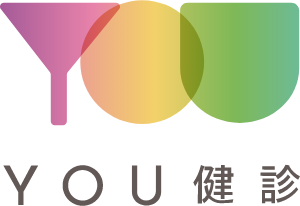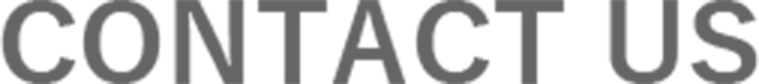株式会社iDA
スタッフHR
interview
現場で働く派遣社員のサポートを行う専門部署、スタッフHR。派遣社員の7~8割が女性であり、長く働ける環境づくりの一環として「女性の健康課題」に着目をしている。今回は、スタッフHRのご担当者様に取り組みや課題についてお話を伺いました。
まずは、事業内容と理念を教えてください。
弊社iDAは、ファッション業界に特化した、人材ビジネス業を主としています。ブランド展開や新規出店計画におけるコンサルティング及び支援サービスなどを提供し、教育、求人サイトの運営、店舗の運営代行など幅広く展開しております。 企業理念は、「働いて夢を叶える=WORKING DREAM®」になります。 店舗やブランドの課題を解決する、販売員の地位向上を実現する、働くことによって夢を実現していこうという弊社の想いが込められています。 ひとり一人のキャリアと向き合い、人と企業の縁をつなぐことで業界を支えていき、共に働く仲間の夢の実現に寄与し、サポートすることこそが我々のミッションであると考えています。
所属されている部署であるスタッフHRの概要を教えてください。

主に、新卒採用や中途採用などの採用活動をはじめ、就業中の派遣社員の全体的なサポートを行っており、適切な労働環境の提供をするために、制度構築や管理を行う部署となっています。 福利厚生の一貫でファムメディコのセミナーなどを企画して、就業者様に情報提供を行っています。
健康経営宣言の中に「乳がん、子宮頸がんの予防啓もうを行います」とありますが、ここに着目したきっかけを教えてください。
弊社は派遣社員も含めて圧倒的に女性が多く、健保の推奨があったことが背景の一つとしてあります。 女性は7割~8割を占めており、社員は30~40代が多く、派遣社員は20~60代まで幅広く就業しております。そのため、女性特有のがんというところにも着目をしています。 健康経営を主体に行っているのは母体であるワールド・モード・ホールディングス株式会社の人事部により行われており、社員向けに取り組みをしています。私たちスタッフHRでは、それらの取り組みを派遣社員へ発信しています。
「女性特有の健康課題」に対して具体的な取り組みを教えてください。
昨年10月にiDA健康保険組合主体で「職場の保健室」を設立しました。健診結果の見方、検査数値の対処方法・不眠や疲れなど、一般的な相談ももちろんですが、不妊治療や妊娠出産の不安についてなどの女性特有のお悩みに関することも相談できます。 健康診断のタイミングにあわせて「職場の保健室」の案内を行っており、実際に相談の反響もあります。 主にメールで相談できるため、時間を選ばず気軽に相談できます。 さらに今年度からは電話での相談受付も開始し、より相談しやすい体制を整えています。 今後も、女性が安心して働き続けられる環境づくりに向けて、相談体制や情報提供を充実させていく予定です。 また、健康に関する取り組みの一環として、iDA健康保険組合から定期的に発信している健康アプリ「カロミル」を使った企画も行っています。食事や歩数を毎日記録することでポイントが貯まり、景品と交換できるなど、楽しみながら健康意識を高められる仕組みとなっております。
上記のような取り組みを導入されて、実際に社員様から反応はありましたか?

定期的に情報発信しているためか、社員の婦人科受診率は7割を超えており、うれしく思っております。 一方で、派遣社員は受診率が社員より少々低いため、これからも情報発信が必要であり、課題となっています。 セミナー開催後は、「勉強になりました」「自分の身体を見つめなおせた」などのポジティブな意見が多くいただいています。
男女ともに従業員がいる中で、女性特有の症状や疾患についての施策を会社に導入する際の障壁や課題があれば教えてください。
今のところ大きな障壁はありませんが、男性にも女性特有の健康知識が同じようにないと理解不足が生まれてしまうのではないかという懸念点があります。 管理職には男性が多いため、部下やパートナー、家族のためにも「女性の健康」がテーマの取り組みに積極的に参加してほしいと思っていますが、取り組みへの参加率は課題のひとつでもあります。 また、デリケートな話題であるため、適切なプライバシー管理の元、女性が相談しやすい制度設計が必要であると思っています。 性差の課題ではないですが、地域ごとに季節感や生活スタイルが異なるため、内容が伝わりにくいケースがあるのも実務上の小さな悩みのひとつです。これらの課題をふまえ、誰もが自分ごととして健康課題に向き合えるような環境づくりを進めていきたいと考えています。
HUGYOUプロジェクトにご賛同いただいたお気持ち、想いをぜひお聞かせください。

女性が多い職場だからこそ、社員ひとり一人が自分自身の身体と向き合って、健康について知る機会を持つことがとても大切だと思っています。HUGYOUプロジェクトを通して「女性特有の悩みや体調の変化」に対する個人の知識を深めることで、不安の軽減や、いざというときに受け入れやすくなると良いと考えています。社員みんなが健康で継続的に働けるように、より良い環境づくりや情報提供をしていきます。